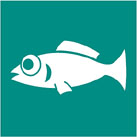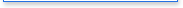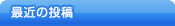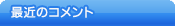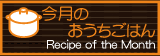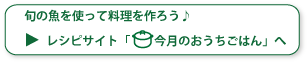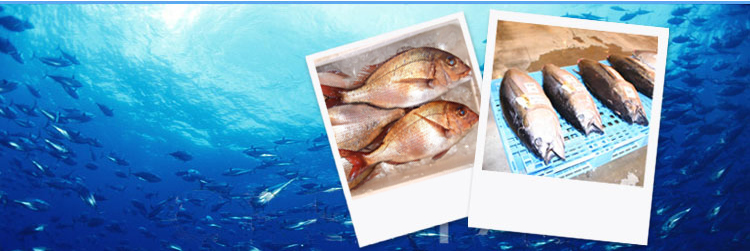
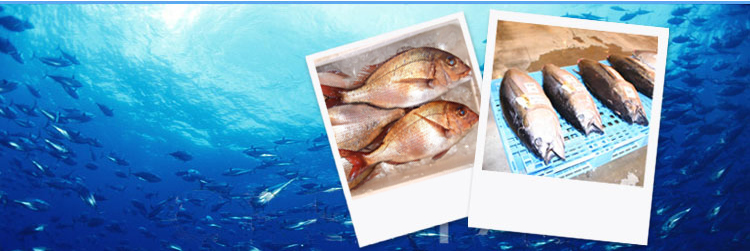
今週のイチオシ!
2010年10月28日 (木)
2010年10月12日 (火)
「ふくい市場フェスタを開催します!」
10月16日(土)にふくい市場フェスタを開催します。
福井市場が生鮮食料品等の流通拠点として、新鮮で安全・安心な商品を提供していることをアピールし、市民の方に市場の重要性を再認識していただくとともに、市場の活性化へとつなげるため、「ふくい市場フェスタ」を開催します。
イベント内容
【水産物部】
鮮魚・塩干物の販売、福井県産の魚の販売、マグロの解体ショーと解体したマグロの販売
【青果部】
青果物の販売、バナナのたたき売り、産地5団体(JA等)と連携した産地商品の販売、
野菜ソムリエによる伝統野菜の試食会
【花き部】
鉢物の販売、フラワーアレンジメント教室
2010年9月 2日 (木)
「商品展示商談会を開催します!」
10月1日(金)に、国内外の各地から様々な水産物を集めて、年に一度の専門家向けの「商品展示商談会」を開催いたします。
食の安全性に関心が高まる中、福井に集まる水産物の多くを見ることができる機会です。
メーカー任せの展示会とは一味も二味も違う内容で、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
※申し訳ございませんが、一般の方は、ご入場できませんので、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
【ここがポイント!】
1.私たちが選び抜いた「売れてる商品」をご紹介します!
2.データ分析に基づいた「売れる売り方」をご提案します!
3.その場ですぐに「商談」ができます!
【開催日時】10月1日(金)10:00~14:00
【開催場所】福井市中央卸売市場内特設会場
住所:福井市大和田町第1号1番地
【主催】福井中央魚市株式会社
【本件についてのお問い合わせ】
福井中央魚市(株) 総務部 藤井
TEL:0776-53-1155
2009年10月16日 (金)
「ほき」

「ほき」はタラ目マクルロヌス科の魚で欧米・ヨーロッパで非常に人気の高い魚です。
主にチリ・アルゼンチンといった南米やニュージーランドの水深200~700mに棲息しており、成長すると全長1m以上になる大型魚です。
ニュージーランドの現地名をとって「ほき」と名づけられました。
年間43万tの漁獲があり、そのうち2万5千tが主に船上で凍結された高鮮度のフィーレ商品として日本に搬入されています。
多くの方は「ほき」という魚の名前を聞いたことがなく、馴染みの無い方が多いと思いますが、フィッシュバーガーに使われる白身魚フライやかまぼこ・ちくわなどの原料に使われ、日本の食卓を陰で支えています。
最近ではムニエルや鍋商材に使われるなど、用途が広がっております。
「ほき」の身は、繊維質で歯ごたえがあり、臭みが全く無いのに脂の乗ったジューシーな風味が好まれ、白身魚としてなくてはならない存在です。
食べ方としては、フライにするのが一番ですが、最近スーパーで焼き物・ムニエル用としての製品を見かけますので、是非試してみてください。
(冷凍部・谷口)
2009年9月 1日 (火)
「商品展示商談会を開催します!」
10月2日(金)に、国内外の各地から様々な水産物を集めて、年に一度の専門家向けの「商品展示商談会」を開催いたします。食の安全性に関心が高まる中、福井に集まる水産物の多くを見ることができる機会です。
メーカー任せの展示会とは一味も二味も違う内容で、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
※申し訳ありませんが、一般の方は、ご入場できませんので、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
【特長】
1.私たちが選び抜いた「売れてる商品」をご紹介します!
2.データ分析に基づいた「売れる売り方」をご提案します!
3.その場ですぐに「商談」ができます!
【開催日時】10月2日(金)10:00~14:00
【開催場所】福井市中央卸売市場 特設会場
住所:福井市大和田町第1号1番地
【主催】福井中央魚市株式会社
【本件についてのお問い合わせ】
福井中央魚市(株) 総務部 藤井
TEL:0776-53-1155
(総務部・藤井)
2009年2月16日 (月)
「海老」

海老は、おせちに使われていることからもわかる通り、縁起のよい食べ物です。字の如く、"老いても、海老のように腰が曲がるまで長生きできますように"と、長寿の意味があります。また、タウリンを非常に多く含む食材で、血圧や、コレステロールの低下に加え、老化防止や美肌効果もあります。
海老を取り扱ううえでは、"美味しい海老を食べてもらいたい"という強い思いがあります。
もちろん、たくさんの種類の海老がいて味も違うのですが、一般的にスーパーに売られているブラックタイガー海老や、バナメイ海老などの、海老の味の差を決める要素に、海水の塩分濃度が関係あると考えられています。海水の塩分濃度が濃い程、身が引き締まり、味が良くなります。また、海老のおいしさを保つには鮮度保持が重要で、漁獲後、いかにえびの温度を低温に保ったまま、短時間で凍結させるかがポイントです。実際に、インドネシアにも行って、確認してきました。
最近、スーパーで、"海水養殖"というシールや表示を見かけませんか?これは、塩分濃度の濃いところで育てた美味しい海老です!!という意味です。
他にも、福井と言えば甘海老、北海道のぼたん海老、富山の白海老、静岡の桜海老、伊勢海老など、日本にも、各産地で美味しい海老がいっぱいあります。次回、違う海老をご紹介させて頂きますが、美味しい海老を食べて、幸せな気分になってもらうことを願って頑張っています。
(冷凍部・吉田)
2008年12月25日 (木)
「数の子」

数の子は元々アイヌに由来していると言われています。ニシンはアイヌ語で「カド」。
「カドの子」が転じて「数の子」になったといわれています。
昔は数の子を干して乾燥させ、保存食として利用しました。戦前は数の子の乾燥品が主流でしたが、現在は加工しやすく家庭でも扱いやすい塩数の子や味付数の子が主になっています。
子孫繁栄を願った縁起物として正月のおせち料理に欠かせない数の子はニシンの卵巣を塩蔵、もしくは乾燥させた加工品です。北海道でのニシン漁獲高が減るにしたがって数の子は高価になり、「黄色いダイヤ」とも呼ばれるようになりましたが、近年アメリカやカナダからの輸入が増え、高めながらも価格は安定しました。
数の子にはたんぱく質が含まれるほか、脂質、抗酸化力を持つビタミンEなどが豊富です。
食べる機会がなかなかないかも知れませんが、お正月に数の子独特のポリッとした歯ごたえある食感を味わってみたらいかがでしょうか。
(特殊・塩干部 塩干チーム 小澤)
2008年11月25日 (火)
「せいこがに」

11月6日に「ずわいがに漁」が解禁になりました。福井の市場でもずわいがにが並びます。オスの「ずわいがに」の甲幅は15cm程になりますが、メスの「ずわいがに」はその半分程にしかなりません。メスの「ずわいがに」が小さいのは、短期間に産卵、抱卵、幼生放出を繰り返すので脱皮ができないため、と言われています。
「ずわいがに」は、オスとメスの大きさが極端に違うため、地域によって呼び名が異なります。「松葉がに」、「間人(たいざ)がに」、「よしがに」などはオスの呼び名で、「めがに」、「こうばこがに」、「おやがに」などがメスの呼び名です。福井ではオスを「ずわいがに」、「越前がに」、メスを「せいこがに」といいます。
オスの「ずわいがに」と比較するとメスの「せいこがに」の値段は数段安くて、家庭でも手軽に味わうことができると思います。実際、私も昔からこの季節になるとよく「せいこがに」を食べています。
「せいこがに」の特徴と言えば、赤い「外子(そとこ)」とオレンジ色の「内子(うちこ)」です。外子はプチプチとした食感が楽しめ、内子は一度食べると癖になる味で、お薦めの珍味です。
「せいこがに」は、資源保護のため1月10日までしか漁獲できません。解禁日からのこの2ヶ月の間に、是非一度お試し下さい。
(鮮魚部・近海物チーム・数馬)
2008年11月17日 (月)
「水魚(みずべこ)」

スーパー等で売られている水魚(みずべこ)は、「ノロゲンゲ」という深海魚です。日本海からオホーツク海にかけての水深300m付近に生息しており、全身はプルプルとしたゼラチン質で覆われ、体は薄いピンク色をしています。
旬は冬から早春にかけてのこの時期です。小骨が多いものの、全身の肉はとても柔らかく、上質な脂がのっています。その為、澄まし汁や鍋物にすると、とても良い出し汁がでます。また、コラーゲン成分たっぷりのプリプリとした肉は、三枚におろして天ぷらや唐揚げにすると美味しく食べることができます。他には、干物にすると上質な脂が濃縮され、食通をうならせる程の旨味を味わう事ができます。
この「水魚」という魚は、最近になって価値が上がってきた魚であり、都会では幻の魚と呼ばれています。その為、「ゲンゲ」に「幻魚」や「幻華」といった洒落た当て字で地方から出荷されます。また、「水魚」のコラーゲン成分を濃縮した栄養補助食品も販売されています。
寒さが厳しくなってきたこの時期、福井では旬の「水魚」を鮮度抜群で食べることができます。寒さで乾燥するこの季節、コラーゲンたっぷりの「水魚」の温かい鍋などいかがでしょうか。
(鮮魚部・刺身物チーム・岡田)
2008年10月14日 (火)
「めぎす」

北陸地方の底曳網漁の代表的な魚のひとつに、「めぎす」があります。正式には「にぎす」と言いますが、福井では「めぎす」の方が一般的な呼び名です。
旬はまさに「秋」で、脂がのって大変美味しい魚です。 鮮度の良いものは、もちろん「刺身」で食べるのが一番ですが、鮮魚の状態よりも、「干物」で出回ることが多いのが、この魚の特徴です。
他に「天ぷら」にしても大変美味しくいただけますが、福井では、「塩いり」と言って、塩水で茹でて、そのまま或いはポン酢で食べる方法が有名です。
先日、漁獲直後に氷水で〆た「めぎす」で「寿司」を握ってもらいましたが、これがまた絶品!
他に社内で聞いてみたところ、ひとりだけ「醤油で煮て食べる」という人がいたのにはびっくりしました。 今度、ぜひ我が家でもチャレンジしてみようと思います。
(開発部・村中)